
What's Triking ?

| 創設者のTony Divey氏 |
|
トライキングは、イギリスのノーフォークにあるTRIKING社のバンガローのような小さなファクトリーで製造された3輪キットカーです。総生産台数は約30年で150弱と非常に少ないですが、日本での知名度は以外とあるようです。モトグッツィのエンジンを使用し、ミッションはグッツィのもの(バックギアはオプション)か車用の5速(トヨタやフォード?)を積んだタイプがあります。リア回りはグッツィのものをそのまま使ったタイプと、特製のスイングアームとホイールにグッツィのファイナルケースを組んだタイプがあります。シャシー(スチール)やボディーパネル(FRP)は少しずつ改良されており、90年代にはフロント回りを チューブラーフレームにしたタイプも加わりました。近年では130馬力までチューンされたエンジンに、大径ローターとブレンボ4ポッドキャリパー(いずれもバイク用) で武装し、カーボンパネルを多用した高性能バージョン「スーパーライト」も登場しました。 2002頃に一時活動を休止しましたが、現在も小さなファクトリーで素晴らしいクオリティーで生産が続けられています。トライキングスポーツカーズ→http://trikingsportscars.co.uk/
|
 |
 |
 |
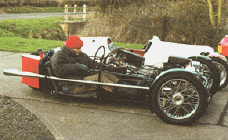 |
| 旧ファクトリー | 路上テスト | ||
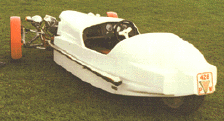 |
 |
 |
|
| 「スーパーライト」 | イベントの様子 | ||



 |
|||
| 2011 英国キットカーショーにて 新生トライキング社のブース | |||
Trikingは こんな車( 輸入されていた当時の雑誌より抜粋、*内容は当時のものです。)
| 「Carマガジン」誌’88年10月号より 【独特のメカニカルな雰囲気を漂わせる、英国製スリーホイラー”トライキング”は、モーガン・スーパースポーツに現代のアレンジを加えた、新旧クロス。オーバーマシン】 1920年代イギリスは、モーターサイクルを三輪化、もしくは四輪化した「サイクル・カー」のブームであった。このサイクル・カーは、主にモーターサイクルから(れっきとした)四輪車へと乗り換えを図ろうとする若者向けに作られたもので、安価な一方、優れた性能を特徴としていた。そして、エンジンは単気筒かVツイン、ボディーは簡単なオープン2シーターが多く、殆どがモーターサイクル・メーカーの販売するものであった。この中で、1920年に生産が始められ1950年まで、作られたモーガン・スリー・ホイーラーは異様なまでの長寿モデルとして、また、ヒルクライムやタイム・トライアルなどのモータースポーツで活躍したことで、最も有名なスリー・ホイーラーということができるだろう。しかし、驚くべきことに、スリー・ホイーラーは、現代の英国では今なお根強い人気を誇る1台である。この種のクルマの集まるイベントには、モーガンに限らずサンフォール、ダルモン、ディルサンといった我が国では馴染み薄いモデルまでが顔を覗かせるから面白い。こんな土壌がいとも簡単にスリー・ホイーラーのレプリカ・モデルを生み出してゆくのだろうが、「トライキング950Rスポーツ」は、それまでロータス社に勤めていたエンジニア、トニーダイビーの作り上げたモーガン・スリーホイーラーである(・・・・・けれど、このトライキングにも、すでにオーナーズ・クラブが設立され、活動を続けているというから、そのスリー・ホイーラーの人気のほどは本当に計り知れないと言った方が良いのだろう)。 さてオリジナルのモーガン・スリー・ホイーラーには、J.A.P.、マチレスなどのモーターサイクル・エンジン(後には水冷4気筒のフォード製もあった)が用いられたのはよく知られるところである。そして、そのエンジンは剥き出しのままフロントに搭載され、メカニカルなモーターサイクルに通じる独特の雰囲気を持っていたが、これと同じくトライキングにはモト・グッチのトランスヴァースVツイン、OHV948ccエンジンが使われている。この空冷エンジンはモト・グッチ・スパダから流用されたもので、71bhp/7200r.p.mのパワーは長いドライブ・シャフトによって。後1輪へと伝えられる。 その特徴的なフロントのワイド・トレッドを形づくるサイクル・フェンダーに収まるのは、サイド・カー用のエイボン製4.00/18インチ・タイヤで、リアのサスペンションはモト・グッチそのままのスウィング・アームである。しかし、各部には当然ながら現代的なアレンジが施されている。まず、フロント・サスペンションは、モーガンの代名詞となったスライディング・ピラーからダブル・ウィッシュボーンに置き換えられ、アルフ・へイゴン製(もちろんモーターサイクル用だ)のコイル/ダンパーユニットが組み合わされる。同様にステンレス・メッシュ・ブレーキ・ホースの先にはそれぞれディスク・ブレーキ(3輪ディスク!)が配され、制動力を高める一方、ステアリングはラック&ピニオンとなるほか、トライキングにはクッションの良いシート、ヴェリア製のメーターの並んだウッド・パネル、そして明るいシビエ製ヘッドランプと耐候性の良い幌などが用意される。 また、輸入元では、このトライキングを発注する際に、我が国の交通事情に合わせたバック・ギア付きをオーダーしており、これにより日本仕様にはトヨタ製5段マニュアル(スターレット用と思われる)が特別に組合わされることになった。 ぎりぎり、2名分のスペースが確保されたトライキングのシートに腰を下ろす。ドアがなく、細長いレッグ・スペースなどはまるでスーパー・セブンに乗る時のように、先ず両足を突っ込んでからお尻をシートに乗せねばないないが、ドライバーズシートが小さい分だけ、苦労させられる。シート・バックはパッセンジャーと共用ながら、シート自体はボルトで位置をスライドさせることが可能。ペダルは、やはりセブン並みに接近するために、細めのシューズを必要とする。 Vツイン・エンジンは、短いクランキングの後、簡単にスタートする。ボディー両側にひき回された英国製のキャンベル・マフラーを通して聞こえるサウンドは大きく、迫力あるものだ。ボディーが軽いせいもあって、発進はスムーズだ。シャフト・ドライブ/スウィング・アームのリア・サスペンションのためか、スタート時に(ホンダ)S600のように軽くリアが持ち上がるが、そのままアクセルを踏み込むとドライヴァはVツインの鼓動と歯切れ良いサウンドに包まれてゆく。そして、エンジンの反応は素晴らしく、予想した通りの加速感を得ることができる。もちろん。スタート・ダッシュは先頭だ。そのまま短めのストロークを持つギアをシフト・アップしてゆくだけでトライキングに乗ったドライヴァは、まるでコマネズミのように混み合った街中を駆け抜けることが可能である。 僅かにホイールベースが短いこともあり、ボディーのピッチングが感じられるほか、乗り心地は予想よりもずっと良い。とは言っても乗用車とは比べものにならないほどサスペンションは固めであるし、路面の凸凹により、車体は常に細かい振動をドライヴァに伝えてくれる。だが、この振動など少しも気にならないほどエグゾースト・ノートは豪快で、低いフロント・ウインドーを越えて顔に当たる風は爽快だ。ラック・アンド・ピニオン式ステアリングは、ほど良くクイック。そして、コンパクトなボディは、時とともに益々ドライヴァとトライキングとの一体感を更に強くしてくれる。モーターサイクルを素晴らしさと、四輪車の安定感を合わせ持つトライキングの実力は、慣らしを終えて箱根のワインディングに持ち込んで(しかも充分に走り込まねば)みなければ本当のところまで理解したとは言えないだろう。が、街乗りだけでもトライキングのつくりの良さ(全体のフィニッシュは水準以上)と、本当のスーパー・スポーツの持つドライヴィングの愉しさ垣間見ることができる。
|
| 「別冊MC」誌’92年7月号より 【モーガンのリバイバル】 イギリスにはモーガンタイプの3輪スポーツ車を’80年台に復活させ、現在も製作を続けている男がいる。それも、モトグッチのオートバイエンジンを流用した簡素な手造りでありながら、現代の交通事情でも十分に通用する、スポーティーで趣味性の高い乗り物に仕立て上げている。 「トライキング」の製作車トニー・ダイビーは、以前はロータス社で働く、テクニカルイラストレーターであった。、またドイツではポルシェや、ドルニエ社(航空機メーカー)の仕事もしていたようだ。エンジニアとしても、20年以上の経歴を持っているという彼は、なによりもモーガンに心酔するマニアであり、’70年代には8台のモーガンを所有していた。 彼が現代版の3輪スポーツを自らの手で造りあげるようになったのも、なんとなくうなづけつ話しである。最初のトライキングを製作したときの動機も、自宅のあるノーフォークから、当時の仕事先であったドイツのミュンヘンまで、簡単に移動できる、信頼性の高い「モーガン」が欲しかったからだという。またJAP製のVツインエンジンが消え去った今日でも、モトグッチのVツインが十分に代役を務めると考えたのだろう。しかもシャフトドライブ車であるモトグッチのギアボックスから、後輪までの駆動系をそのまま流用すれば、残った部品のほとんどは、手造りでも製作可能になる。 さらにブレーキや電装系に最新の部品を使用すれば、これはもう昔のモーガンとはまったく別物の近代的なスポーツマシンが生まれてしまう。ちなみに標準仕様のトライキングの車重は355kgで、これに搭載されるモトグッチのノーマルエンジンの出力は71bph/7200rpmであり、そのパワーウェイトレシオが非常に優れているのがおわかりいただけるだろう。またタイヤも(エイボン製のサイドカー用とはいえ)現代の物なら、昔のモーガンより格段に進化したトランクションとグリップが得られる。 さらにトライキングには、82bph/7400rpmの「スーパースポーツ」仕様が用意されており、製作者であるダイビー氏本人が今でも使用している1号車は、デロルト50mmの気化器を使って100bphを引き出し、最高速は200km/h以上を示しているという。
【トライキングの実力】 車体まわりでトライキングとモーガンの最大の相違点は、フレーム構造にある。モーガンでは、先端のエンジン部から後ろに伸びるドライブシャフトチューブを中心に構成したチューブラーフレームの上にボディーを搭載しているが、トライキングでは鋼板(A16ゲージ)を使用して溶接で組み立てられた箱型のバックボーン(プロペラシャフトトンネルを兼ねる)と、タブ状の車体を一体とした準モノコック構造なっている。 前輪は、上下でアーム長の異なるダブルウィッシュボーンが採用され、マルゾッキ製の可変ダンパー付きサスペンションが取り付けられている。この結果、フロントフレームはロータスエランによく似た形状のものとなっている。この前輪部の強力な構成は、まさに純スポーツカーといえる仕様であり、ロッキード製のディスクブレーキと合わせて、トライキングのコーナーリング性能を並のスポーツカー以上のものにまで高めている。 しかもこれら前輪部分の部品のほとんどが手造りの自製品なのが面白い。フロントフレームのアップライトや、ウィッシュボーンアームから、肝心なアクセルスイベルまでが、鋼板やスチールチューブそ溶接した自作品なのである。 フロントハブはアルミ(LM24)鋳造したあと、自工場で切削加工し、焼き入れを行っている。またkのハブに合わせるために、ブレーキディスクも特注で鋳造したものを削り出しているようだ。つまり、主要な部品で市販品を使っているのは、ロッキードのブレーキキャリパーと、マルゾッキのサス、それにリム/スポークとタイヤくらいのものである。このレイアウトからは、徹底的なまで簡素に、そして経済的に自作して、しかも可能な限りスポーツ仕様に組み立てるというポリシーがうかがえる。 こういった「手造りマシン」も、過去に無数のバックヤードビルダー達が生まれたイギリスでは、当然の結果のように造られてしまうだろうが、普段、大量生産させる製品ばかり見ている目からすれば「なるほど」と改めて感心させられてしまう部分も多い。 例えば、「手造りですよ」と言わんばかりのウィシュボーンアームの電気溶接のビードなどを見ていると、思わず「これどのくらいの強度があるのだろう?」と素朴な疑問を抱いてしまう。しかしこの製作者は、トライキングの1号車を造り上げたあとすぐに、イギリスや本土を縦断するランズエンズトライアルや、ヒルクライムなどの競技に積極的に参加を続け、耐久試験を繰り返しえいたようだ。また公道での走行距離も、10年前の時点ですでに160000kmに達していたというから、経験的にも相当の自信を持って製作しているのであろう。製作者本人がマニアックなユーザーであり続けるもとが、何よりもそのマシンの信頼性を証明してしまう。 トライキングの駆動系は、当初よりモトグッチのギアボックスから後輪までをそのまま使用していたために、前進5速のみで後退はできず、変速比もファイナルまでモトグッチと同じであった。変速は左手でシフトレバーを前後させて操作するが、オートバイと同じ5速リターンのため、2輪に慣れていないドライバーには、ニュートラルが出し辛く、そのためファシアにはニュートラルランプがつけられていた。 ところがドイツの車検制度に適合させるにはリバースギアが不可欠のために、4輪のギアボックスの流用を行うようになった。現在製作中のほとんどは、このリバースギア付きの仕様であり、日本に輸入された今回の試乗車もこのギアボックスが付いいる。これはトヨタセリカ(おそらく)の5速ギアボックスで、クラッチハウジングをスチール製として溶接加工で自作し、モトグッチのクランクケースとトヨタのケースを巧妙に接合している。またモトグッチの後輪ハブからドライブシャフトまでは、そのままトヨタのギアボックスに接続される形で使用されている。この4輪よう変速機を流用したために、1速からの立ち上がりや、4速と5速(OD)の間は少し離れすぎている気がする。ただし全体のバランスや、リバースギアが付いたことの利便性を考えれば、申し分ない出来であろう。
【箱根での試乗】 試乗したのは、調布市近辺の市街地と中央自動車道、そして箱根の仙石原から乙女峠にかけてである。このトライキングに乗ると、まず鋭敏な旋回性能に驚かされる。少しオーバーステア気味のセッティングなのだが、これが不思議なほどの安定性を備えており、まったく不安がない。通常のサイドカーよりも重心が低く、またトレッドが広いために、非常にクイックなハンドリングを示すのであろう。これは3輪特有のコーナーリング特性であり、30年以上前にドイツで造られたキャビンスクーター「メッサーシュミット」も同様にクイックなハンドリングを見せてくれる。ただしトライキングの場合はそのスピードがまったく異次元のものであり、最近の小型スポーツカーよりも一段と速く(本当に)、タイトコーナーをすり抜けてしまうのである。また車中が軽いために強力なトルク感があり、市街地での中低速走行を長時間続けてもドライバーが疲れることはない。日常の足として使っても十分に実用的である。これはモトグッチが中低速トルクの太い、高速ツーリング用エンジンなのがそのまま功を奏したものと思われる。また高速道路でも、最新の1ℓクラスの乗用車と同等以上にクルージングすることもできる。 このトライキングでは、例えば4輪のロータススーパーセブン(これも低重心で旋回性能が高い)のようなロケットスタートは望むべくもないが、もう少し低い速度でのドライビング、とくに小刻みに曲がりくねった峠道や、市街地でその本領を発揮する。もしエンジンをチューンして、より強力なパワーを加えれば、後輪をパワースライドさせてさらに簡単に旋回することも容易だろう。 トライキングは(体力的な理由などから)オートバイより楽に、オートバイ的な走行を楽しみたい、という方には格好のマシンと言えよう。しかしオートバイを乗りこなしす元気のあるライダーや、サイドカーの魅力に取り憑かれてしまったマニアにとっては、単に4輪的な乗り物にすぎないかもしれない。 ただ、ヘルメットを被らず、緑あふれる小道をトライキングに乗って疾走するときの爽快感には、捨て難い魅力を感じてしまう。この点に関しては、オートバイよりもオートバイらしいと言えるだろう。 モトグッチユニット等は、製作者のダイビー自身がバンに乗っを運転して年に1度イタリア、マンデロにあるモトグッチ工場に出向き、まとめて購入してくるのだという。以前 ダイビーがトライキングに乗ってイタリアまで行ったときに、この変わった3輪スポーツがリノ・トンティー(モトグッチVツインの開発リーダー)の目にとまり、以来エンジンからファイナルケースまで、モトグッチ社より直接供給されるようになったという。
|
| 「NAVI」誌’92年8月号より 【トライキングはピストンだった!?】 モーガン・スリーホイラーの、「の・ようなもの」 ある日、突然、トライキングに乗ることになった。”TRIKING”とは1910年から52年までつくられたモーガン・スリーホイラーの、「の・ようなもの」である。 ある日、突然と言っても、本当はそんなに突然ではない。編集長の指令から当日まで、10日間ほどの猶予はあった。けれど乗る17時間前まで、僕はVWゴルフに乗っていた。乗り終えてから26時間後には、外人専用 のはとバスに乗った。そのような日常においてトライキングに乗るのはやはりそういう突然なことである。 「明日、すごいの乗るんだよ。トライキングての。モーガンのスリーホイラーって知ってる?・・・・・・・知らないだろ。三輪車。タイヤ3つ・・・・バイクみたいな・・・・・・クルマみたいな・・・・・・、すごいヤツ・・・・・知らないだろ」前日の食卓でそう話しても、一切の運転免許を持たないヨメさんからは、ほとんどなんの反応もなかった。
三浦半島まで行こうという決意が、とたんにグラついた
翌日、横浜市港北区のファクトリーで、ブリティッシュ・グリーンのトライキングに対面する。 工場に着いたたとき、ショップオーナーのSさんは、なにやら深刻な面持ちでエンジン調整に励んでいた。ちょっと調子が悪いとかで、たしかにアイドリングが続かない。一般道を走って三浦半島まで行こうという決意が、とたんにグラつく。 英国ノーフォーク州ノリッジでつくられるこれは、モーガン・スリーホイラーの志を流用した乗り物である。”機会仕掛けの虫”のような外観は、ボートテールのスリーホイラーに似ているが、同じではない。メーカー自身、決してモーガンのコピーと呼んでくれるなと言っている V字型の鋼板フレームに剥き出しで搭載されるエンジンは、71ps/7400rpmのモトグッチ1000用の950cc空冷Vツイン。セリカ用5段ギアボックスから伸びる長いプロペラ・シャフトが後ろ1輪を駆動するが、最終的にチェーン駆動だったスリーホイラーに対して、こちらはモトグッチのシャフトドライブがそのまま使われている。 そのほか、フロントのサスペンションは、スライディング・ピラーではなく、鋼管のダブル・ウィッシュボーン。リアは1/4リーフではなく、モトグッチのスイング・アームとコイル。ブレーキは前後すべてディスク。全長=2997×1511mmのボディー外寸も、ご先祖様よりだいぶ大きい。というように、モーガン・スリーホイラーの忠実なレプリカントであろうとする意図はまったく窺えない。あくまでやはり「の・ようなもの」である。 「アッ、わかったわかった」 FRPのフロントフードに腕を突っ込んでいたSさんが声を上げた。点火系がリークしていたところを発見したらしい。これにてエンジン問題は一件落着したようだったが、しかし、今度は天候問題が悪化して、曇り空からパラパラと雨が落ちてきた。結局、近場の田園調布市沿線に向かうことに決める。
果たしてこれを”クルマ”と呼んでいいものか?
低いサイドシルを跨いで、地上高30cmあるやなしやの低い運転席にもぐり込む。英国スポーツカーの常で、アレッと思うほどトーボードは遠く、シートクッションも固定式だが、バックレストの角度をナットで調整できるので、身長165cnの僕でもなんとか不自由ない運転姿勢がとれる。太いセンタートンネルで仕切られたコックピットは、それほど窮屈ではないものの、足元はスーパーセブンなみにギュッと狭い。 果たしてこれを”クルマ”と呼んでいいものかどうかわからないが、運転の操作系そのものは、普通のクルマとまったく同じで、3つのペダルを始め、ギアやウインカーのレバーもあるべきところにある。合板でできたダッシュボードのつくりはかなり雑だが、英国のバックヤード・ビルダーの仕事はだいたいこんなものである。 ペダルの間隔がおそろしく狭いので覗き込んでみると、15cmほどの幅に3つがひしめいている。フォーミュラ・フォードあたりから拝借したペダル・ユニットらしい。しかし、いまさら文句を言っても仕方ない。 足応えのあるクラッチを踏み込んで、いよいよキーをひねる。ガッ・・・・ガッ・・・・、苦しげな金属音をたてて、高い圧縮比と戦うピストンが2回空振りをしたあと、モトグッチVツインは、突然ズドーンと目を覚ました。 「障害物があったら、前輪で踏んでいったほうがいいですよ。後ろはかなり突き上げが大きいですから」 轟々たるエンジン音に包まれたコックピットのはるか上から、ツナギ姿のSさんが声をかける。3輪車ならではのアドバイスだ。 「あと、コレ、気をつけて下さい」 と言いながら、腕にある何ヶ所かのシミを見せる。乗り降りの際、ボディサイドの丸裸の排気管にやられたヤケドの跡だった。
トライキングはもはやピストンだ!
トライキングはどんな乗り物か。 これはエンジンそのものである。エンジンに抱かれて走るクルマ。かつてBDRコスワースを積むスーパーセブンの記事を書いたときにも、そんな表現を使ったと思うが、ならばトライキングはそれ以上だ。もはやピストンそのものである。 800rpmのアイドリングでは、本当にピストンの上下動が手にとるようにわかる。ホンダ・ビートなみにストロークの小さいシフトレバーを操りながら加速してゆくと、ズドドドドドドと玄翁(カナヅチのでかいやつ)で打ち続けるような音を振動が前方から押し寄せる。1万回転まで目盛られた回転系にレッドゾーンの表示はないが、6000rpm以上の高回転を使うには、かなりの野蛮がいる。 カタログ・データによると、ゼロヨンは16秒フラット。71psとはいえ、車重は(車検証で)420kg(メーカー公称値は355kg)だから、それぐらいは当然だろうが、ためしに1、2速を7000rpmあたりまで回して加速すると、速いというよりなにより、とにかく凄まじい。 ウインドスクリーンは思いのほか有効で、80km/hくらいまでなら、それほど風の巻き込みはない。だが、トライキングの場合、走行中、ガラスの内側で首をすぼめていては、楽しさ半減というものだ。サイドシルから肘を出し、少し頭を右に傾けると、18インチのエイヴォンを覆うサイクルフェンダーがすぐそこに見える。レーシー極まりないサスペンションも、ロッキードのブレーキ・ユニットも見える。さらに上体をせり出せば、大人の頭ほどもあるVツインの片われが見える。動くメカが全部見えるという非現実性が、実になんとも夢を見ているようで面白い。 発進の際、一瞬、まずお尻がピョコンと上がるスイング・アームの癖を除けば、舗装路の上を普通に走る限り、3輪車ゆえの違和感はとくに感じられない。ただ、ダートとなると話はべつで、砂利道では簡単に尻を振る。 坂を斜めに上るようなシュチュエーションも苦手で、そのへんは、補助輪をつけた自転車が、かえって機動力を削がれるのに似ている。
こんな突拍子のないものが存在できる英国がうらやましい
英国のワンメイクレースを走るトライキングは、ドライバーの体重移動で片側前輪をリフトさせながら曲がるらしい。つまり、直線は3輪、カーブは2輪。とある場所で編集部のA君に見張りをお願いして、体重移動のインリフト・コーナーリングに挑戦してみたが、とてもとてもできるものではない。後輪は僅かにスライドするが、それ以上のことはなにも起こらなかった。1輪少なくても、いや、1輪少ないからこそ、操縦の奥はクルマよりも深いのだろう。 Sさんによると、これはバイクとサイドカーの合いの子だという。つまり、決してクルマではない。たしかにそうかもしれない。僕としては、もうちょっとスムーズなエンジンが欲しいと思ったが、そんなものは所詮、堕落した4輪乗りのタワゴトで、モトグッチはもちろんのこと、ドゥカティや、ハーレーや、あるいは、かつてのカワサキ・ダブワンを知る2輪乗りなら、このビッグVツインにむしろ親近感を覚えるかもしれない。 しかし、それにしてもこういものに乗ると、こんな突拍子もないものが生まれ、存在できる英国という国が、つくづく羨ましく思える。 その英国に、トニー・ダイビーという一人のエンスージャストがいた。エンジニアの彼は、8台ものモーガン・スリーホイラーを所有し、海を越えて、ドイツへの出張にもこれで出かけた。だが、さすがに時間がかかる。そこで、もっと速い、快適な、現代のスリーホイラーができないものか、と思い至り、ついには自らつくってしまったのがトライキングの歴史の始まりである。 ちなみに、日本での価格は車検込みで487万円。今回の試乗車を含めて、まだ3台しか輸入されていない。
トライキング
モトグッチ1000用のV型2気筒950ccOHVエンジンと、トヨタ・セリカ(FRモデル)用のトランスミッションと、旧タイプのロータス・エランのようなバックボーンフレームでできている英国製の3輪車。タイヤは3つとも径18インチ/幅4インチのエイヴォン製のバイク用。サスペンションはフロントがダブル・ウィッシュボーンで、リアがモトグッチのスイング・アーム。ブレーキは前後ディスク。価格は487万円。オプションはコノリーレザー、カムカバーのバフがけなどで、すべて相談次第だ。 92年モデル以降は、トライキングの生産累計100台の達成記念として、ボディーがFRP製になり、リアに16インチインチの自動車用タイヤが装着される。また82psのモトグッチ・ルマン1000用エンジンも装着可能になる。日本には88年から輸入が開始されているが、その当時は納期が1年で、本格的な輸入販売は去年からである。 |
|
トライキングはグッツィの様々なエンジンを使用し、またオプションも豊富なことから、1台1台仕様が異ると言ってもいいほどです。 |
エンジン
|
60年代から現代に至る、モトグッツィのビッグツイン系(OHV・2バルブ)を使用しています。年代はグッツィの生産年。 【オルタカバーが横に長いタイプ は、オプションの「高出力オルタネーター」装着車です】 |
|
|
|
|
|
|
------ラウンドヘッド-------
|
-----スクエアーヘッド-------
|
---スクエアー4バルブ(OHC)-
|
--スクエアー+スーパーチャージャー--(アフターパーツを使用した改造です)
|
ミッション
|
本来ミッションは 、グッツィのモノをそのまま使っていてバックは無かったのですが、ドイツの車検制度用にトヨタのミッションを組むようになってこらはこちらが主流になりました。 現行はグッツィのリターン式(エンジンにより5速か6速)で、オプションで社外のバックギアユニットを付けるようです。
|
|
|
|
| 車用5速(主にトヨタ)は特製のクラッチハウジングにミッションが取り付けられます。シフトレバーの根本から前に伸びるリンケージ(黒い棒)で前方にある ミッションの切り詰められたレバーに繫がっています。ストロークはかなり短いです | グッツィのミッションをそのまま使用したタイプは写真ようにシフトゲートが一文字に切られ、シーケンシャル風の操作になります。新しいエンジンでは6速もあるので、バックを付ければこちらの方が、より楽しめそうです |
インテリア
|
基本的にウォールナットなどの木目が綺麗で豪華なインパネが多数なようです。一番寂しい仕様はベニヤですが、逆にクラシカルで好きです。 シートや内張りはレザーでカーペットもあり、この手の少量生産キット カーとしては豪華ではないでしょうか。
|
 |
 |
 |
 |
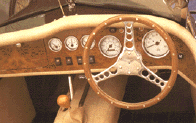 |
 |
|
内装いろいろ・・・・・・特注でなんでも可能なのか?オーナーのカスタムなのか?1台1台さまざまですね・・・ |
||
その他
 |
 |
 |
 |
|
フロントスクリーンのある車両も幌も装着可能。2011年以降はブルックランスレーシングスクリーンも選べるようです。 |
幌の画像。熱線もヒーターも無いから・・・雨辛そうです乗り降りも辛そう・・・。珍しい初期型の固定フェンダー | ||
|
|
|
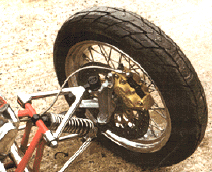 |
 |
|
オリジナルのロッカーカバー(ヘッドカバー)も数種類あるようです。 |
レース車両(スーパーライト))速そうですね。チューブラーフレームのフロント回りとブレーキに注目!車高低過ぎ! |
||
耐久テスト!?
|
製作第1号車の「CNG415T」は、耐久テストを兼ねて様々なレースやラリー、ヒルクライム等に参加してきました、誕生より今まででなんと約600000マイルを走破! 今なお走り続けています。基本的な 骨格は変わってないのかもしれませんが、エンジンやフロント回りは年を重ねるごとに、少しずつ造り直されているようです。
|
 |
| ↓ |
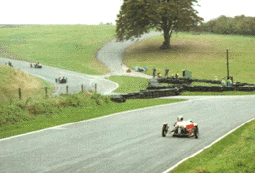 |
|
↓ |
|
|
そして日本では・・・
| 1990年前後に、川崎のショップさんが極僅か(数台)輸入されたそうです。
そちらで輸入されたうちの1台を宮崎駿さんが所有されている(いた?)ことが有名で、そのお陰でこの車を知っている方が多いのだと思います。私が
調べて判っているのは下記の11台です。 これ以外の情報をお持ちの方、またオーナーの方、是非ご連絡下さい。お待ちしております。 (画像はイメージです)
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
宮崎氏所有? |
千葉県? |
福島県
|
九州?
|
群馬県? |
長野県 |
関西方面? |
中京方面? |
愛知県 |
福島県? |
長野県? |